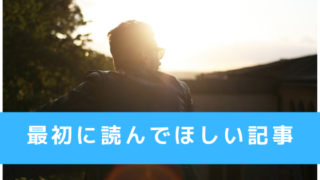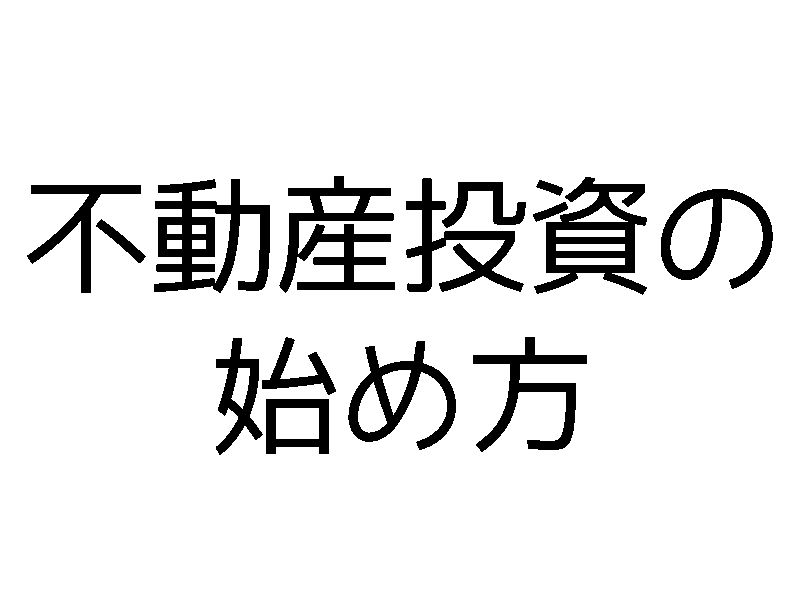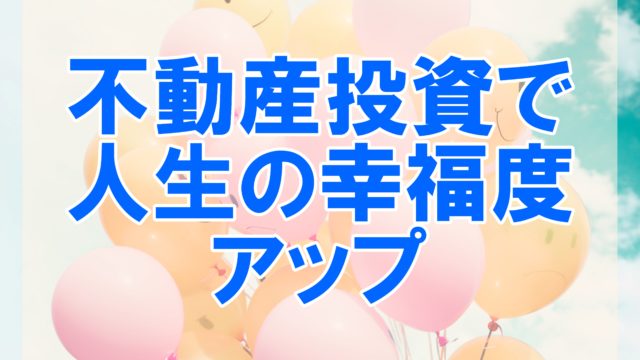こんにちはJOJOです!
シェアハウス「かぼちゃの馬車」の販売・運営元であるスマートデイズがとうとう民事再生法の適用を申請しましたね。
それと軌を一にするように、金融庁はスマートデイズの融資を一手に引き受けていたスルガ銀行に対して緊急検査を行いました。
各種報道によれば、シェアハウスオーナーの貯金残高を改ざんするという不正行為に、スルガ銀行自体が関与していた可能性があるとのことです。
スルガ銀行は果敢にリスクテイクしながら、高い収益性を上げる独自のビジネスモデルを行っており、日本の銀行の中では面白いプレイヤーでした。
それが、収益性&リスクテイクという部分だけが突っ走ってしまって、肝心のリスク管理がおざなりになってしまったようです。
ただ、スルガ銀行の独自の高収益モデルは、旧来の日本の硬直した銀行体質を変えるパワーと可能性を持っていると考えます。
今回のことはしっかり反省して、さらなる成長を遂げてほしいなと思っています。
ただ、今回の金融庁の査察を受けて、不動産投資環境は大きく転換点を迎えることになります。
なぜならば、より一層、不動産投資向けの融資が厳しくなるからです。
今回、過剰融資の問題になっているのはシェアハウスです。
ただ、スルガ銀行全体の不動産投資向け融資におけるシェアハウスの割合なんて大したものじゃないです。
それよりも、通常のアパート・マンションに対する融資のほうが圧倒的に規模が大きいです。
金融庁の査察が入るということは、シェアハウスだけでなく、その他大勢のアパート・マンションに対する融資についてもメスが入ると予想しています。
なぜならば、一般のアパート・マンションの購入資金として、スルガ銀行から融資を受けたオーナーの中には、返済が苦しくなって困っている人たちが沢山いるからです。
金融庁は、以前からアパート・マンションに対する過剰な不動産投資への危機感も強めていました。
そのため、今回、金融庁がスルガ銀行の査察を行うことで、シェアハウスだけでなく、一般のアパート・マンションに対する融資についても厳しい指導が入ることが予想されます。
そうすると、今後ますます不動産投資向けの融資は厳しくなります。
今後、不動産投資向け融資が厳しくなることを踏まえて、どのような投資物件を購入していくべきかを説明したいと思います。
スルガ銀行が融資を絞ると、物件が売れなくなる
スルガ銀行が一般のアパート・マンションに対する融資を厳しくすることによって一番困るのは、既にスルガ銀行から融資を受けて物件を購入してしまったオーナーです。
不動産投資の世界では、スルガ銀行でないと融資がつかない物件というのが沢山あります。
つまり、スルガ銀行の融資がストップすれば、スルガ銀行の融資を使って購入した物件は、今後売れなくなる(融資がつかなくなる)ことを意味するのです。
スルガ銀行が融資していた物件の特徴
スルガ銀行だけが融資をしていた物件の特徴は以下の通りです。
- 地方にある耐用年数を超過した築古RC/鉄骨
銀行は基本的に建物の構造ごとに国が定めた法定耐用年数以内でないと融資をしません。
例えばRCですと法定耐用年数が47年ですので、築30年のRCの場合は、残り17年しか返済期間を設定できません。
それが、スルガ銀行の場合は、法定耐用年数ではなく、銀行独自の年数カウントを使っていたため、築30年超えの鉄骨やRCであっても、30~35年という長期の返済期間を設定してくれました。
返済期間を長く設定すれば、毎月の返済金額が減少するので、毎月のキャッシュフローが増えることを意味します。
そのため、スルガ銀行は不動産投資家にとっては、とてもありがたい存在でした。
- フルローン/オーバーローンが可能
もう一つのスルガ銀行の大きな特徴は、頭金をほとんど入れなくても、全額フルローン融資が出ていたことです。
スルガ銀行から融資を受けたオーナーの中には、フルローン以上のオーバーローンを受けている人も少なくありません。
つまり、物件の購入代金に加えて、不動産会社への仲介手数料を含んだ諸費用分まで全額融資してくれるのです。
そのため、物件購入時には、全て融資で賄うことができるので、手元の現金は1円も使う必要がありません。
中には、不動産購入費用とは別で、利用用途無制限の無担保融資(1,000-2,000万円)まで受け取った方もいます。
つまり、不動産を購入すればするほど、手元資金が潤沢になるという不思議な現象が起きるわけです。
そのため、もともと手元現金が少ない不動産投資初心者にとっては、非常に心強いパートナーだったわけです。
- 金利が高い
ここまでは、不動産投資家にとっては、良いこと尽くしのスルガ銀行ですが、世の中そんなに甘くありません。
スルガ銀行の金利は、他の金融機関に比べると高い水準です。
大手都市銀行が1%前後の金利で不動産向け融資をしてくれるのに対して、スルガ銀行の貸出金利は4-4.5%。
高いリスク(地方、法定耐用年数オーバー、フルローン)を積極的に引き受ける代わりに、収益性の高い融資を行うという特殊なビジネスモデルです。
確かに金利は高いのですが、その分融資期間を長く設定してくれるため、毎月のキャッシュフローは比較的余裕が出てきます。
そのため、この高い金利にも関わらず、毎月安定した賃貸経営ができるということで、スルガ銀行は不動産投資家間でとても人気でした。
融資がつかないので、物件の価格が下落する
それが、今回の件で、スルガ銀行の不動産投資に対する融資が厳しくなったらどうなるでしょうか?
スルガ銀行で融資を受けた物件を売却する場合は、買い手もスルガ銀行で融資を受けるのが一般的でした。
つまり、スルガ銀行の中で、物件がぐるぐると回っていたのですね。
それが、スルガ銀行の融資がストップすると、最後に物件を購入した人は売ることができなくなります。
融資を受けて、買える人がいなくなるわけですから。
具体的に言うと、地方・築古・鉄骨/RCの3要素を持っている物件は今後確実に売れなくなります。
最終的には、プロの不動産業者が現金で購入してくれる可能性はあるのですが、その場合、物件価格は購入時の良くて半分、ほとんどは1/3くらいの価格まで買い叩かれることになります。
現在の日本の金融機関の中で、スルガ銀行と同じような姿勢で積極的に投資物件に融資を行っている銀行はありません。
最後のゲートキーパーであるスルガ銀行が手を引くと、売却出口がなくなってしまうのです。
そのため、スルガ銀行が得意としていた地方・築古・鉄骨/RCの3要素を持っている物件の価格は下落していくと予想できます。
物件を購入してしばらくの間は、前の賃借人を引き継いでいるため、そんなに経営は苦しくありません。
ただ、購入して1年程度経つと、退去する人も増えてきます。
地方・築古・鉄骨/RCの3要素を持っている物件は利回りは高いですが、客付け難易度が高いものがほとんどです。
そのため、客付けノウハウのない投資初心者の方の中には、空室を解消できない人も少なくありません。
スルガ銀行から融資を受けたオーナーのほとんどは、上場企業のサラリーマンのように高属性の方です。
そのため、空室が続いても、しばらくは自分の給料から不動産投資のマイナス分を補填できます。
ただ、いずれは限界が来ます。
給料で補填できるのは、長くて1年程度であることが多いです。
そして、とうとう、毎月の給料で補填できなくなると、いよいよ売却して損切りしようとするオーナーが増えてきます。
すると、損切りするオーナーに引きづられる形で、不動産価格が下落を始めます。
不動産価格が下落を始めた時には、既にスルガ銀行の融資が閉まっているでしょうから、どうにも売れません。
そのため、現金で購入できるプロの不動産業者が購入する水準(いわゆる業者価格というやつです。市場価格の半分~7割くらいのケースが多い)まで、大幅に下落していくことが予想されます。
現在、スルガ銀行で融資を受けているオーナーの皆様にとっては厳しい現実でしょう。
まだ不動産投資を始めていない方はラッキーだと思います
僕のブログを読んでくださっている皆様の中にはこれから不動産投資を始めようと思っている方も多いと思います。
そんな皆様はラッキーです!
なぜならば、ババ抜きのババを免れたからです。
今までの時代のように、実績のない初心者でもフルローンで不動産を購入できた時代は終わります。
そのため、人によっては、不動産投資を始めるチャンスを逃したと思う方もいるかもしれません。
でも、ヘタに不動産投資を始めて、出口の無い物件を掴んでしまうことほどキツイことはありません。
不動産投資は基本的に規模が大きいので、一度失敗すると、立ち直るのがとても難しいです。
大きく勝つことよりも、負けないことのほうが大事なのです。
今後、負けない物件とは
では、今後はどのような物件を購入していけば良いでしょうか?
ズバリ、出口がしっかりと取れる物件を購入することです。
つまり、数年保有した後でも、サクッと売却できる物件ということ。
具体的に言うと、次の条件を満たした物件を購入することです。
- 都市部
- 新築もしくは、築浅
- 木造よりも、鉄骨/RC
- 物件価格が1億円以内
もちろん、上記3つ全てを満たせる物件なんてそうそうありません。
あっても、めちゃくちゃ利回りが低いです。
そのため、3つのうちどれかは妥協しないといけないですが、少なくとも2つを満たせる物件が良いでしょうね。
その理由をそれぞれ述べてみます。
都市部の物件
地方に比べて都市部の物件は、購入できる投資家の数が多いです。
なぜならば、基本的に銀行は、購入者の居住地の近くの物件でないと融資をしてくれません。
地銀、信金はまさにこの傾向が当てはまります。
ということは、住んでいる人が多い地域の物件のほうが、融資がつきやすいということ。
そのため、日本で一番人口の多い東京の物件は、一番売れやすい物件ということになります。
新築もしくは築浅
銀行は基本的に法定耐用年数以内でしか融資期間を設定してくれません。
そのため、残存法定耐用年数がたっぷり残っている新築もしくは築浅物件は、次の買い手にとって融資が組みやすい物件なんですね。
法定耐用年数が47年もあるRCですと、新築から10年保有しても、まだ残り37年もあります。
30年以上融資期間が取れれば、毎月の返済金額も減らすことができます。
木造よりも、鉄骨/RC
建物の構造によって、法定耐用年数は大きく異なります。
- 木造:22年
- 鉄骨:34年
- RC:47年
基本的に銀行は法定耐用年数以内でしか融資期間を設定してくれないことを鑑みると、耐用年数の短い木造よりは、鉄骨やRCのほうが有利ですね。
物件価格が1億円以内
物件の規模が大きくなればなるほど、購入のために必要な融資金額も増えていきます。
もちろん、融資金額が大きくなればなるほど、融資のハードルは上がります。
そのため、売却しやすさという観点からすると、規模が小さい方が有利です。
都市部の場合でも、物件価格が1億円を超えると、購入できる層が限られてくるので、できれば1億円以内の物件を購入したほうが安全でしょう。
まとめ
上記4つの要素を2つ以上満たす物件種別は次になりますね。
- 都市部の新築木造アパート(一棟モノ)
- 都市部の区分所有マンション
- 地方都市の築浅鉄骨/RCマンション(一棟モノ)
これらの物件は、誰もが欲しい物件になります。
そのため、利回りはどうしても低くなってしまいます。
じゃあ、不動産投資なんか意味がないじゃないかと思うかもしれません。
でも、不動産投資には、他の金融商品には無い優位性があります。
それは、融資を受けて、投資ができるという点です。
そのため、利回りが低くなったと言われても、投資規模を大きくすることができるので、まだまだ稼ぐことができる投資手法だと思います。
もちろん、今までのようにフルローンは受けれなくなるでしょうし、僕自身は受けるべきではないと思います。
ありきたりの話になってしまい恐れ入りますが、不動産投資の王道はある程度の頭金を入れて、毎月のキャッシュフローに余裕のある状態を維持し、安定した賃貸経営を行うことです。
そして、高値で売れるタイミングであれば、売却を行う。
売っても良し、保持しても良しの状態を目指すのが理想です。
欲張って大きく儲けることを考えるよりも、まずは負けない投資をすることが大事です。
これから不動産投資を始めようと思っている方の参考になれば幸いです。
関連記事
お金をかけずに不動産投資のノウハウを学ぶ方法
https://asoburo.info/realestate/how_to_start/3590/
初心者が不動産投資を始める前に身につけるべき知識・ノウハウのまとめ記事